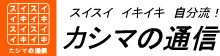首都圏エリア
KG高等学院 水道橋(東京)
認定NPO法人高卒支援会運営
2022.12.13 不登校からの立ち直り

引きこもり中学生・高校生 現場から見た引きこもりの特徴

今回は引きこもり中学生・高校生の実態を実際の引きこもり現場の視点でお伝えしていきたいと思います。
少しでも状況が類似している方はご注意ください。お早めに相談機関にご相談していただくことをおすすめします。
「不登校」と「ひきこもり」は似ている言葉ですが、文部科学省による定義ですと、
不登校は高校生までの病気や経済的な理由以外で「年間30日以上欠席」したもの
一方で引きこもりは仕事や学校に行かず、家族以外との交流をほとんどせず「6か月以上続けて自宅」にひきこもっている状態を指します。
一方で現場を見ていると、欠席日数が長ければ長いほど引きこもりになる傾向が高くなりますが、必ずしも欠席日数が短いから引きこもりではないと判断されるのは危険です。
実際に欠席日数が30日未満でも引きこもり状態の子は非常に多いです。
以下の写真は私が実際に訪問をした不登校期間2ヶ月の子の部屋です。
1ヶ月過ぎた頃にはこのような状況になっており、不登校期間は関係ないと実感した現場でした。他人事ではなくいつでもこうなる可能性はあります。
現場から見た引きこもりの特徴
引きこもりは一定期間に達すると急になるものではありません。
徐々に引きこもりの状態になっていきます。
徐々になっていくので同じ家にいるご家族はその異変に気づかないものです。
異変にいち早く気づけるように、今回は現場からみた引きこもりの特徴を挙げていきます。
お子様が以下のような状態になってきたら引きこもりの前兆といえますので注意が必要です。
①ゲームやタブレットの利用時間が伸びる。または伸ばすように言ってくる。
引きこもりになる子の初期状態として起こることがこれです。直近1年で16名の引きこもりの自宅訪問をしましたが、
14/16で88%の子どもたちはゲームやタブレットの利用時間が伸びています。
更に利用時間を伸ばすように言ってきた子どもはそのうちの13/14と90%以上という数字が出ました。
男の子の場合、時間が伸びないと暴言を言う、物を壊す、親に手を出すという子もいました。
特に引きこもり期間が長いほどそういったことをしてしまう傾向にありました。
②部屋を閉める。部屋から出てこない時間が増える。
自分の部屋がある場合は、要注意です。引きこもりが加速します。
部屋から出てこない時間が増えると部屋から出てご飯を食べなくなっていきます。
部屋の前にご飯を置くようになると完全にアウトです。
ご飯を部屋の前に置くタイプの家は毎年1名くらいの割合しかいませんが、全て部屋の中の状況が分からない状態です。
部屋にはいると食べ物や飲み物が散乱しており臭いも酷く非常に危険な状態といえます。
③連絡先を消す。連絡がつかない
引きこもり状態とは全てをシャットダウンしている状態です。
なので、友人や知人、家族の返事もしなくなります。
そして全ての関わりをなくすために連絡先も消します。
こうなると外部からのアプローチができなくなるため引きこもりが加速します。
文部科学省の定義にもある通り、家族以外との交流がなくなることで引きこもりに繋がってしまう原因となります。
人との交流がなくなり、ゲームやネット動画、snsに逃げて現実逃避をする。
自分の状況を正常に判断できなくなり引きこもり期間が半年、1年と伸びていきます。
そうならないためには正常な判断ができるように外部との繋がりが必要です。
保護者の方は、まず上記の状態に一つでも当てはまっていないかチェックして頂き、一つでも当てはまっているのであれば一刻も早く引きこもり相談機関にご相談してください。
年末年始も引きこもりの支援します!
枠に限りがございますのでお早めにご相談ください。
ぜひご相談お待ちしております。
相談する
不登校・引きこもりについてはもちろん、中退・留年・転学・編入・学業不振・非行・発達障害など様々なお悩みの方からのご相談をいただいています。予約フォームの入力をしていただくと面談のご予約ができます。
少しでも状況が類似している方はご注意ください。お早めに相談機関にご相談していただくことをおすすめします。
不登校と引きこもりの違い
「不登校」と「ひきこもり」は似ている言葉ですが、文部科学省による定義ですと、
不登校は高校生までの病気や経済的な理由以外で「年間30日以上欠席」したもの
一方で引きこもりは仕事や学校に行かず、家族以外との交流をほとんどせず「6か月以上続けて自宅」にひきこもっている状態を指します。
一方で現場を見ていると、欠席日数が長ければ長いほど引きこもりになる傾向が高くなりますが、必ずしも欠席日数が短いから引きこもりではないと判断されるのは危険です。
実際に欠席日数が30日未満でも引きこもり状態の子は非常に多いです。
以下の写真は私が実際に訪問をした不登校期間2ヶ月の子の部屋です。
1ヶ月過ぎた頃にはこのような状況になっており、不登校期間は関係ないと実感した現場でした。他人事ではなくいつでもこうなる可能性はあります。
現場から見た引きこもりの特徴
引きこもりは一定期間に達すると急になるものではありません。
徐々に引きこもりの状態になっていきます。
徐々になっていくので同じ家にいるご家族はその異変に気づかないものです。
異変にいち早く気づけるように、今回は現場からみた引きこもりの特徴を挙げていきます。
お子様が以下のような状態になってきたら引きこもりの前兆といえますので注意が必要です。
①ゲームやタブレットの利用時間が伸びる。または伸ばすように言ってくる。
引きこもりになる子の初期状態として起こることがこれです。直近1年で16名の引きこもりの自宅訪問をしましたが、
14/16で88%の子どもたちはゲームやタブレットの利用時間が伸びています。
更に利用時間を伸ばすように言ってきた子どもはそのうちの13/14と90%以上という数字が出ました。
男の子の場合、時間が伸びないと暴言を言う、物を壊す、親に手を出すという子もいました。
特に引きこもり期間が長いほどそういったことをしてしまう傾向にありました。
②部屋を閉める。部屋から出てこない時間が増える。
自分の部屋がある場合は、要注意です。引きこもりが加速します。
部屋から出てこない時間が増えると部屋から出てご飯を食べなくなっていきます。
部屋の前にご飯を置くようになると完全にアウトです。
ご飯を部屋の前に置くタイプの家は毎年1名くらいの割合しかいませんが、全て部屋の中の状況が分からない状態です。
部屋にはいると食べ物や飲み物が散乱しており臭いも酷く非常に危険な状態といえます。
③連絡先を消す。連絡がつかない
引きこもり状態とは全てをシャットダウンしている状態です。
なので、友人や知人、家族の返事もしなくなります。
そして全ての関わりをなくすために連絡先も消します。
こうなると外部からのアプローチができなくなるため引きこもりが加速します。
引きこもりになりかけている時に必要なこと
文部科学省の定義にもある通り、家族以外との交流がなくなることで引きこもりに繋がってしまう原因となります。
人との交流がなくなり、ゲームやネット動画、snsに逃げて現実逃避をする。
自分の状況を正常に判断できなくなり引きこもり期間が半年、1年と伸びていきます。
そうならないためには正常な判断ができるように外部との繋がりが必要です。
保護者の方は、まず上記の状態に一つでも当てはまっていないかチェックして頂き、一つでも当てはまっているのであれば一刻も早く引きこもり相談機関にご相談してください。
年末年始引きこもり・不登校集中解決キャンペーン
年末年始も引きこもりの支援します!
枠に限りがございますのでお早めにご相談ください。
ぜひご相談お待ちしております。
相談する
不登校・引きこもりについてはもちろん、中退・留年・転学・編入・学業不振・非行・発達障害など様々なお悩みの方からのご相談をいただいています。予約フォームの入力をしていただくと面談のご予約ができます。
学習等支援施設からのお知らせ
在校生・卒業生の声
| 首都圏エリア | |
|---|---|
| 東北エリア | |
| 東海エリア | |
| 甲信越エリア | |
| 近畿エリア | |
| 中国エリア | |
| 四国エリア | |
| 九州エリア | |
| 沖縄エリア |
| ネット指導制 |
|---|